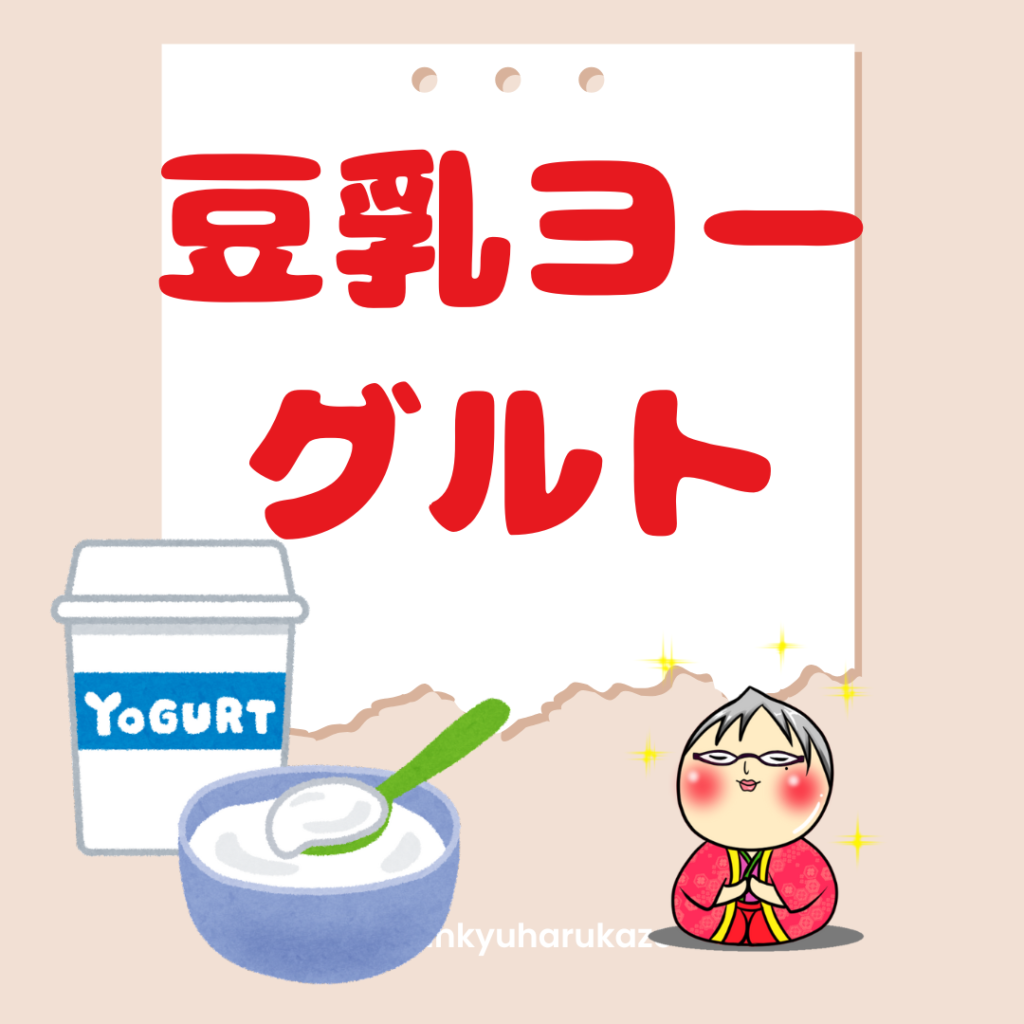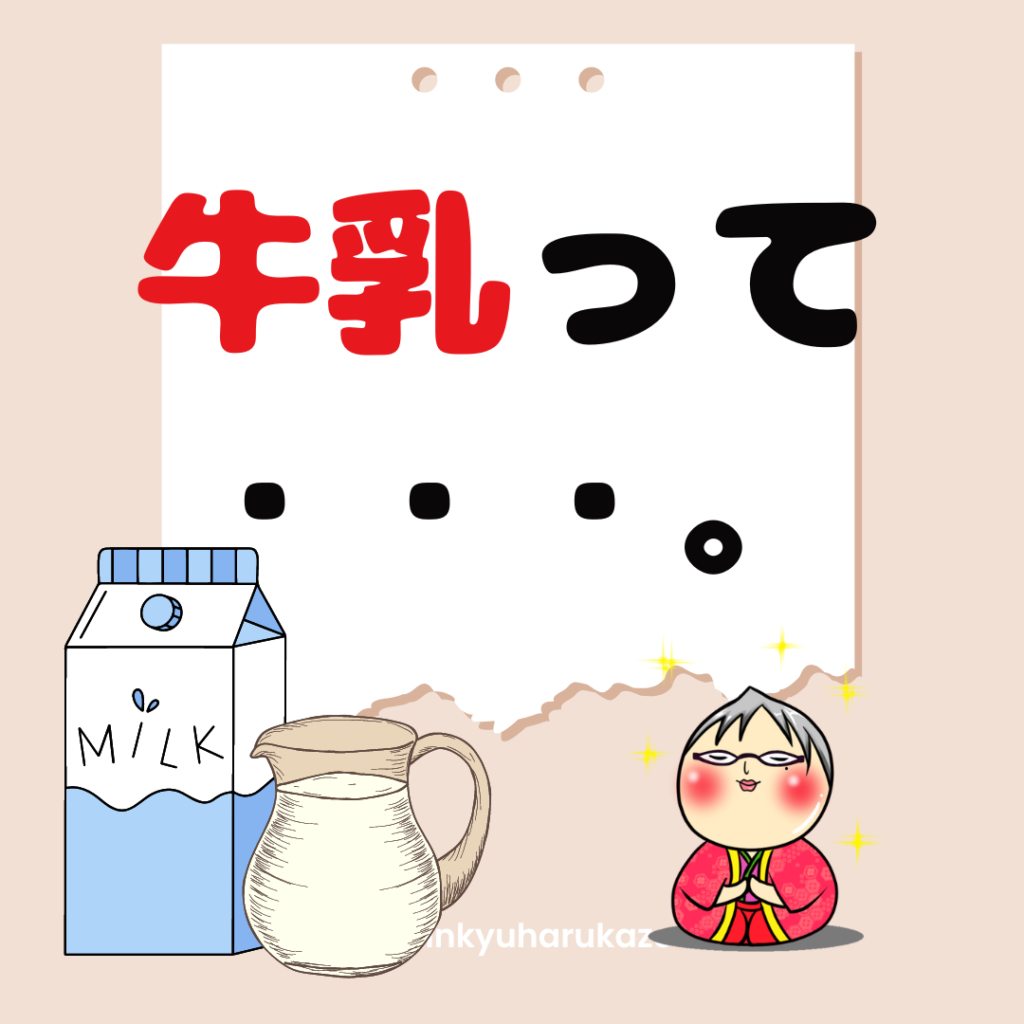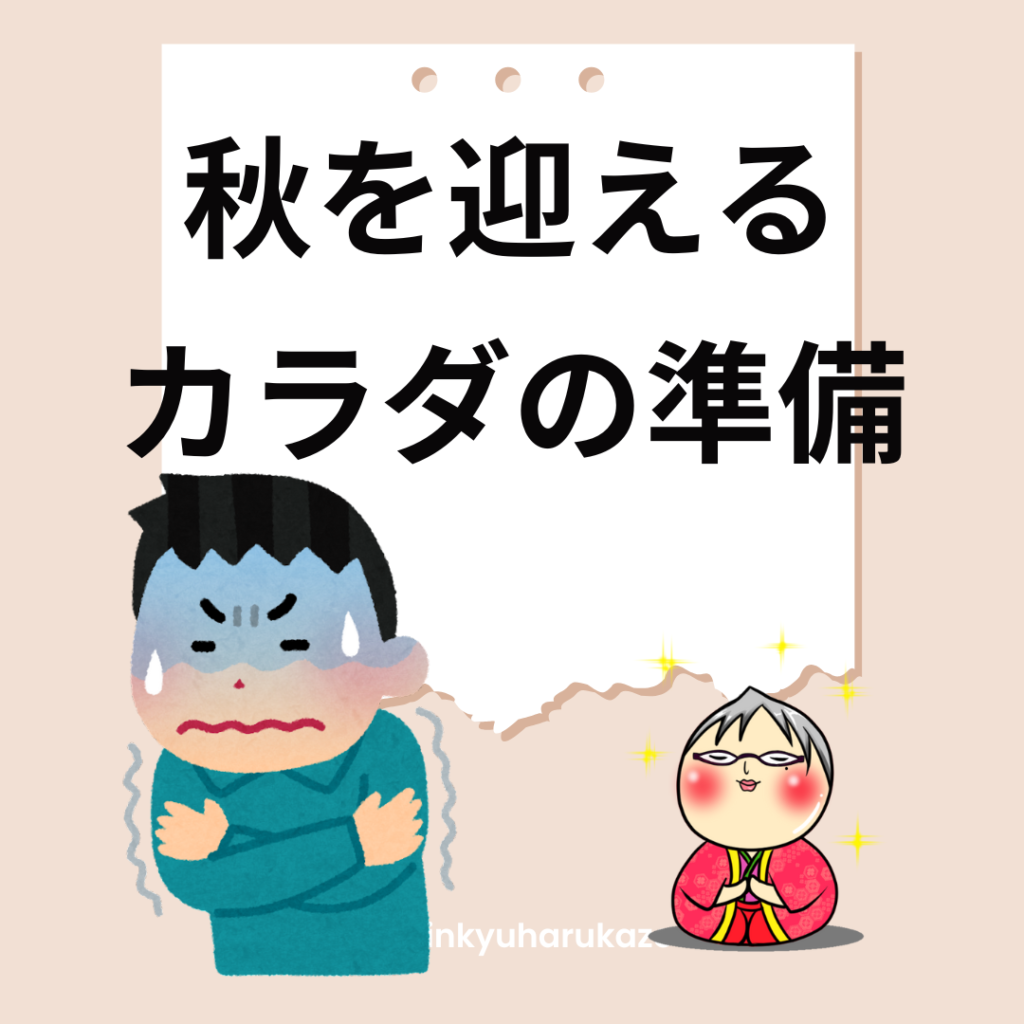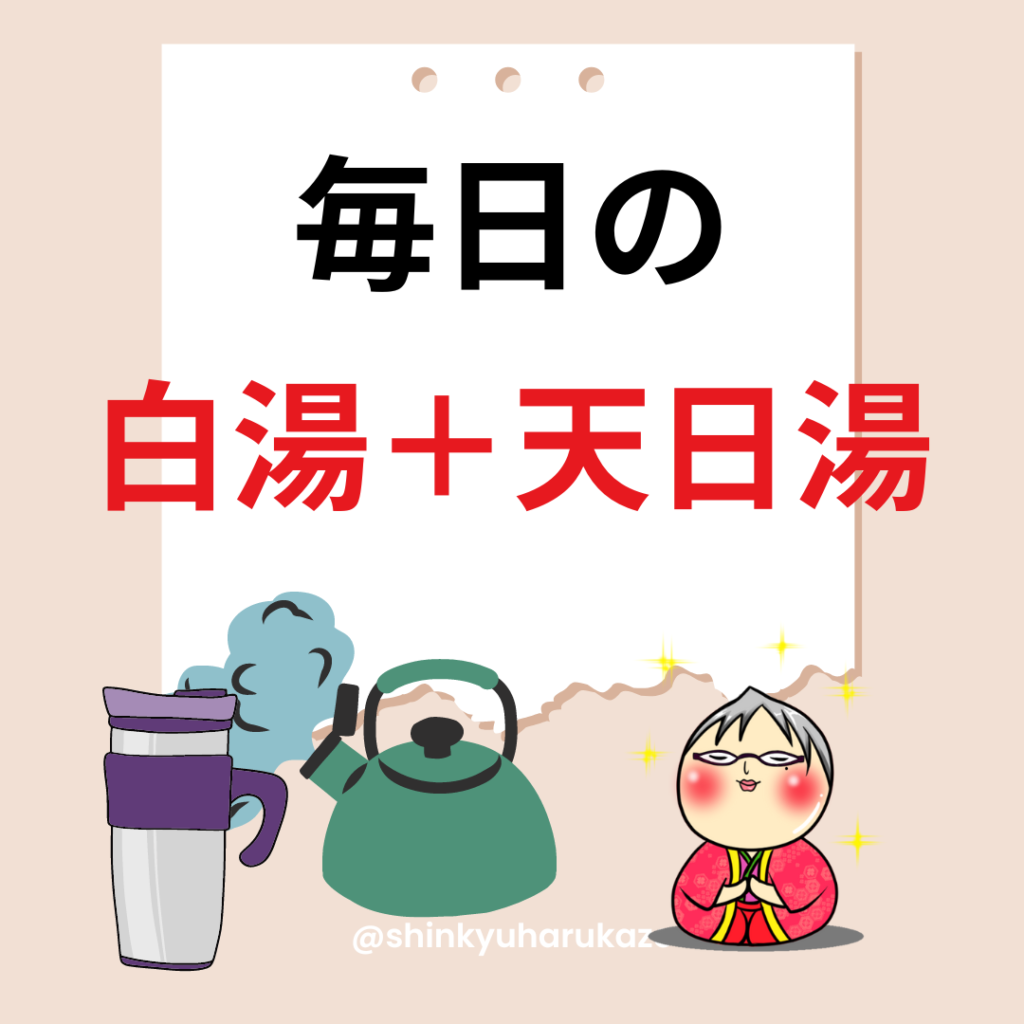養生よもやま話
-

台風と不調
病院に行くほどではないけれど、どうにも体調が優れないときがあるものです。頭痛、めまい、食欲不振、吐き気、気分の落ち込みなど・・・。そんなとき観察してみると、同じパターンが繰り返されていることに気が付くかも。台風が近付いてくるときに調子を... -

豆乳ヨーグルト
通常のヨーグルトは牛乳から作られます。牛乳がカラダに合わない人はヨーグルトも合わないわけですが、ヨーグルトは好きという人は多いかもしれません。豆乳ヨーグルトは、大豆から作られた豆乳を発酵させて作られる植物性のヨーグルトです。牛乳でお腹が... -

牛乳って・・・。
お腹が弱っているときに牛乳を飲むのは控えておきましょう。牛乳はカルシウムやビタミンDなどが豊富で、健康に良いとされていますが、日本人の約3人に2人は牛乳を消化しにくいカラダを持っています。体質的に、牛乳に含まれる乳糖を分解する酵素(ラクター... -

弱った脾胃にお米
夏は脾胃が弱りやすく、食欲不振や消化不良をきたすと、不調が長引いてしまいます。というのも、1日3食なら都度、お腹に飲食物が入っていく度に、脾胃を酷使してしまうからです。だからといって、食べないわけにもいきません。そこで弱った脾胃を立て直... -

甘酒の作り方
乾燥米麹と炊いたご飯で作る。ご飯は白米だと甘味が強く、玄米だとくどくない滋味の甘さになる。乾燥米麹はスーパーで手に入る。麹菌は50℃くらいで死滅するのでお水を入れてぬるいくらいがよい。低温調理のできる器具だと簡単にできるし、炊飯器の保温機能... -

夏の疲れに甘酒
この夏の疲れが出ていませんか?長く高温と湿気の環境にいると、暑さがカラダに侵入して、熱がこもった状態になり、夏バテ、食欲不振に陥ることがあります。疲れた胃にやさしいものをとって、元気を回復したい、そんなときに甘酒は適しています。「甘酒」... -

入浴締めの冷水
暑い時期から始める秋冬への準備入浴の締めに膝から下に冷水をかける。冷水と言っても、このように暑いと水が温められていて、ぬるい水になっているかもしれません。しかし温水と比べて温度差があるので、腠理を閉める練習にはなるでしょう。習慣になっ... -

秋を迎えるカラダの準備
腠理の開闔。難しい字ですね。「そうりのかいごう」と読みます。腠理とは皮膚のきめのことで、開闔とは開くと閉じる、の意味。腠理はカラダの表面で、外気に応じて開けたり閉めたりを自律的に行っています。汗腺の開け閉めをイメージしたらよい。夏... -

夏バテ 胃腸をいたわる
お盆を過ぎる頃、日が落ちると虫の声が聴こえるようになり、相変わらずの高温であっても確実に秋の訪れが近づいていることを感じます。この頃、夏の疲れがどっと出やすい時期です。夏が終わりに近づき、朝晩が涼しくなると、からだがついていけなくなり、... -

毎日の白湯+天日塩
白湯のマイボトル。温かいまたは常温の水をこまめに飲むのがおすすめです。特に暑い時期や運動時には、熱中症や脱水予防のため水分だけでなく塩分も一緒に補給することが推奨されます。ペットボトルの水やお茶の代わりに天日塩を加えた白湯をマイ保温...