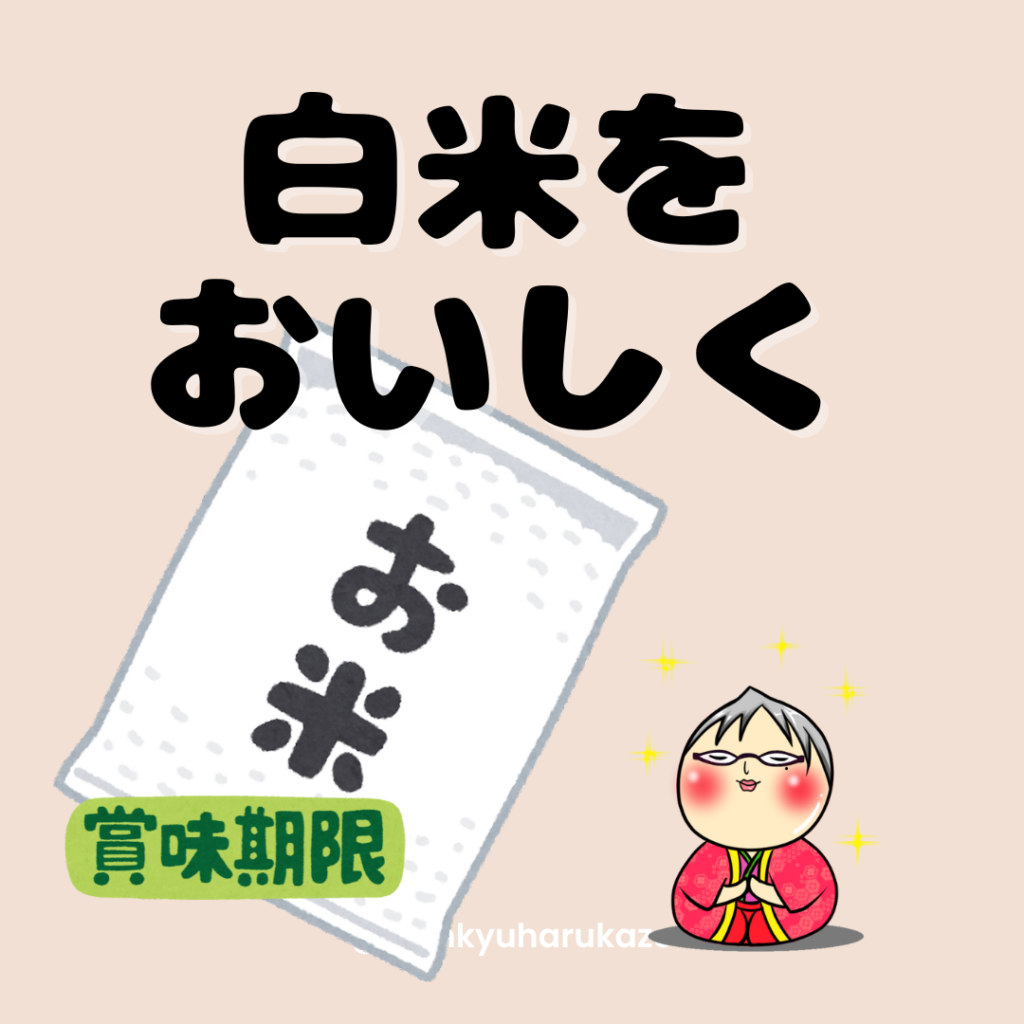養生よもやま話
-

2025大晦日
本年もご愛顧ありがとうございました。お会いできたすべてのみなさまに感謝申し上げます。来年もたくさんの幸せにめぐりあわれますことお祈りいたします。 -

冬至2025
本日、冬至点を通過しました。冬至は「二十四節気」の一つで、冬至の期間は小寒の前日まで、2025年では12月22日から2026年1月4日までです。この時期は北半球で昼が最も短く夜が最も長くなる日(冬至日)を境に、日が少しずつ長くなりますが、寒さは厳しく... -

足のつり予防に。ストレッチとマッサージ
足のつり、けいれんは突如起こり、短時間でも強い痛みはイヤなものです。予防には、ストレッチが効果的です。寝る前などにふくらはぎと太ももの裏(ハムストリングス)をじんわりと伸ばすストレッチを習慣にしましょう。大切なのは、筋肉をリラックスさせ... -

秋分
今日は秋分の日。すでに秋分点である9月23日午前3時19分を過ぎました。秋分は、昼と夜が同じ長さ、陰と陽が同じ分だけある、均衡する点です。全く均衡している状態なら、どちらにも傾かず、静止したままです。バランス点は通過点であって、分量の差がたち... -

されど、口内炎
体内に余分な熱がこもると発生しやすい病のひとつに口内炎があります。軽く見られがちですが、食べ物がしみたり、話す時に痛んで、さらに噛んだりして、煩わしいものです。余分な熱は特性として上昇し、カラダの上部、つまり頭部や顔面、口唇、歯、心臓、... -

夏バテ防止、むくみとりにすいか
すいかは水分が豊富で、ビタミンA・B1・B2・Cをはじめ、カリウム、カルシウム、リン、鉄などのミネラルを含みます。カラダを冷やす作用が強く、この夏のような厳しい暑さが続く時期にはうってつけです。運動した後など、熱を持ったカラダは一切れのすいか... -

夏至
本日、夏至点を通過しました。夏至は、二十四節気のひとつで、一年で最も昼が長く夜が短い”日”であるとともに、”期間”としての意味があります。「夏至」の期間は、一般的に「夏至」の日から次の節気「小暑」の前日までとされています。2025年の「小暑」は7... -

お米、ちゃんと食べてる?
最近、お米の価格が上がってきたことで、ますます“米離れ”が心配されています。戦後、日本の食卓はどんどん洋食化し、それとともに米の消費量は減少の一途をたどっています。減反政策で姿を変えた水田も、簡単には元に戻りません。私たち日本人にとって、... -

白米をおいしく
メディアはコメの話題で溢れています。今日はおコメについて。精米後の白米は表面の糊粉層や胚芽、ぬかが取り除かれているため、表面積が大きく空気(酸素)に触れやすいため、玄米やもみ殻付きの米よりも酸化のスピードが速いです。酸化が進むと、味が落... -

精気の虚2
五臓(肝心脾肺腎)の精気の虚が、あらゆる病の始まりです。五臓の持っている各々の性質によって、例えば肝の精気の虚があれば、血を伸び伸びと発散させたり、貯蔵する力が弱まります。心の精気の虚があれば、生命の根本的な元気が弱まります。脾の精気の...